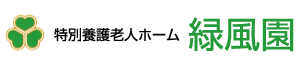特別養護老人ホーム緑風園 看取りに関する指針
1.当施設における看取り介護の考え方
看取り介護とは、近い将来に死に至ることが予見される方に対し、その身体的・精神的苦痛、苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して生き抜くことができるように日々の暮らしを営めることを目的として援助することであり、対象者の尊厳に十分配慮しながら終末期の介護について心をこめてこれを行なうことである。
2.看取り介護における医療行為の選択肢
看取り介護は、対象者が人生の最終ステージにおいて最期の瞬間まで、安心・安楽に過ごすことを目的としており、そのために考え得る医療・看護について、医師の判断で都度適切に行うこととする。その際に、延命処置(心臓マッサージ・除細動(AED)・人工呼吸・輸血)などは行わず、点滴も対象者の苦痛にならないように、必要最低限の対応とする。食物を経口摂取できなくなった場合も、経鼻経管栄養・胃ろう造設・IVH対応を行わず対応する。医療機関への緊急搬送や入院治療等も行わずに、最期の瞬間まで施設で安楽に過ごすことができるように対応する。
3. 看取り介護の具体的支援内容
①利用者に対する具体的支援
Ⅰ.ボディケア
・バイタルサインの確認 ・環境の整備を行なう ・安全、安楽への配慮
・清潔への配慮 ・栄養と水分補給を適切に行う ・排泄ケアを適切に行う
・発熱、疼痛への配慮
Ⅱ.メンタルケア
・身体的苦痛の緩和 ・コミュニケーションを重視する
・プライバシーへの配慮を行なう ・全てを受容してニーズに沿う態度で接する
Ⅲ.看護処置
・医師の指示に基づき必要な点滴や酸素吸入等の看護処置を看護職員によって行なう。
②家族に対する支援
・話しやすい環境を作る ・家族関係への支援にも配慮する
・希望や心配事に真摯に対応する ・家族の身体的、精神的負担の軽減へ配慮する
・死後の援助を行なう
4.看取り介護の具体的方法
①看取り介護の開始時期
看取り介護の開始については、医師により一般に認められている医学的知見から判断して回復の
見込みがないと判断し、かつ、医療機関での対応の必要性が薄いと判断した対象者につき、医師
より利用者または家族にその判断内容を懇切丁寧に説明し、看取り介護に関する計画を作成し終
末期を施設で介護を受けて過ごすことに同意を得て実施されるものである。
②医師よりの説明
Ⅰ.医師が①に示した状態で、看取り介護の必要性があると判断した場合、看護職員又はソーシ
ャルワーカーを通じ、当該利用者の家族に連絡をとり、日時を定めて、施設において医師より
利用者又は家族へ説明を行なう。この際、施設でできる看取りの体制を示す。
Ⅱ.この説明を受けた上で、利用者又は家族は利用者が当施設で看取り介護を受けるか、医療機
関に入院するか選択することができる。医療機関入院を希望する場合は、施設は入院に向け
た支援を行なう。
③看取り介護の実施
Ⅰ.家族が施設内で看取り介護を行なうことを希望した場合は、介護支援専門員は医師、看護
職員、介護職員、栄養士等と共同して看取り介護の計画を作成すること。なおこの計画は医
師からの利用者又は家族への説明に際し事前に作成しておき、その際に同意を得ることも考
えられること。
Ⅱ.利用者または家族の希望により多床室で看取り介護を行う場合は、他の同室者の同意を得
て、適時、本人または家族の意思を確認すること。
Ⅲ.看取り介護を行なう際は、医師、看護師、介護職員等が共同で入所者の状態又は家族の求
め等に応じ随時、利用者又は家族への説明を行ない同意を得ること。
Ⅳ.施設の全職員は、利用者が尊厳を持つひとりの人間として、安らかな死を迎えることがで
きるように利用者または家族の支えともなり得る身体的、精神的支援に努めること。
特に肉親の死と向かい合う家族の悲嘆感に配慮して、その哀しみから立ち直る支援に努め
ることとする。
5.看取り(ご逝去)時の協力医療機関との連携体制
当施設は協力医療機関である三愛病院との連携により三愛病院の医師が死亡確認を行う。家族への
連絡方法については事前に意思を確認しマニュアルに沿って行う。
6.看取り介護終了後カンファレンスの実施について
Ⅰ.看取り介護が終結した後、看取り介護の実施状況についての評価カンファレンスを行うものとする。
Ⅱ.介護支援専門員またはソーシャルワーカーは、看取り介護対象者の遺留金品引渡しの際、家族等に別紙様式におけるアンケート用紙への記入協力を求める。家族等がこれを拒否する際にはアンケート用紙の記入は求めない。
Ⅲ.介護支援専門員は遺留金品引渡し終了から1週間以内に「看取り介護終了後カンファレンス」を開催する。参加職員は相談員、看護職員、介護職員、栄養士、その他必要に応じた職員とする。この際、家族によるアンケート結果がある場合は、これを資料として提出する。
Ⅳ.カンファレンスは別紙(看取り介護終了後カンファレンス報告書)の内容に基づき話し合いを行い報告するものとする。
7.責任者
看取り介護については、看護師のうち1名を定めて、これを責任者とする。
その他
(平成18年3月作成)
附則:平成18年9月7日より、この改正指針を実施する。
附則:平成20年4月1日より、この改正指針を実施する。
附則:平成20年9月1日より、この改正指針を実施する。
附則:平成26年4月1日より、この改正指針を実施する。
附則:平成27年4月1日より、この改正指針を実施する。
附則:平成29年10月31日より、この改正指針を実施する。
附則:令和5年2月10日より、この改正指針を実施する。